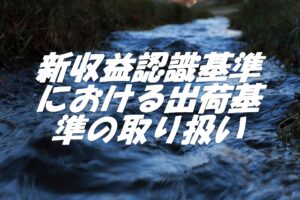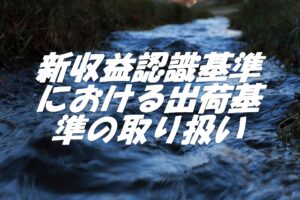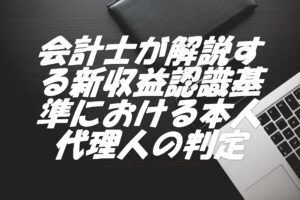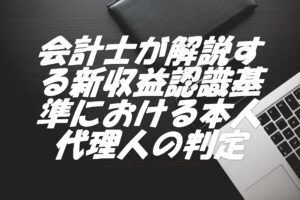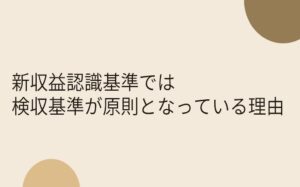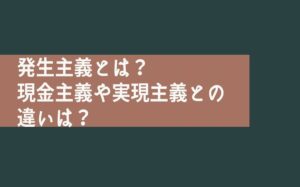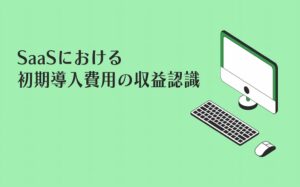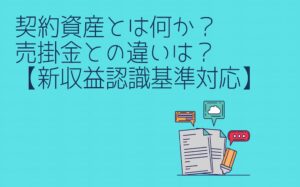悩んでいる経理
悩んでいる経理預り売上ってそもそもどういうこと?
預り売上は無条件に売上計上していいの?
預り売上を計上するための要件とは?
上記の悩みにお答えします!
- 預り売上の定義
- 新旧会計基準での預り売上の会計処理
- 新収益認識基準で預り売上が認められるための4要件
従来の会計基準での預り売上の会計処理


預り売上の定義
そもそも預り売上の定義ですが、
預り売上とは、客先からの注文や契約は存在するものの、在庫の出荷を伴わず在庫を保有した状態での売上高の計上を言います。
一般的に売上とは、客先から注文が入り、注文に対応する商品や製品を出荷し、相手側で納品・検収されたタイミングで売上高として計上されるものです。
しかし、相手側の理由で出荷できないケースがあります。例えば以下のとおりです。
- 受け入れ側(客先)の倉庫に余裕がないから出荷を待ってほしいと言われるケース
- 受け入れ側の生産スケジュールの関係で出荷を一部ストップしているケース
- そもそも商慣習上、自社での倉庫保管が条件となっているケース
このような場合には、商品や製品が出荷されないため客先側でも商品や製品が検収されません。しかし、預り売上の対象となっている在庫と、これから販売予定の在庫では両者に見た目で区別つきません。
このような場合に無条件で売上高として計上すること(収益として認識するか)が認められるのかが論点となります。では、会計基準は預り売上をどう取り扱っているのでしょうか。以下のとおりです。
従来の会計基準における預り売上の会計処理
結論から記載すると、
従来の会計基準では、預り売上についてどのような場合に収益として認識できるかが明記されていませんでした
新収益認識基準が導入されるまでの従来の基準では、収益は、財又はサービスを提供して対価を取得した段階で収益を認識することとなっていましたが、それ以上の言及はありませんでした。
そのため、従来の会計基準では、預り売上を売上として計上するかどうかは各会社の判断によるところが大きくなっていました。
しかし、2021年4月以降導入された新収益認識基準では、預り売上について売上高として計上できる場合の要件を定めることとなりました。次にその要件を見ていきます。
新収益認識基準における預り売上の取り扱い


新収益認識基準における預り売上(請求済未出荷契約)の定義
新収益認識基準では預り売上を請求済未出荷契約と定義し、以下のとおり記載しています。
- 新収益認識基準では、預り売上を請求済未出荷契約と表現している
- 請求済未出荷契約とは、企業が商品又は製品について顧客に対価を請求したが、将来において顧客に移転するまで企業が当該商品又は製品の物理的占有を保持する契約である
特に2行目が預り売上の定義となりますが、「将来において顧客に移転するまで企業が当該商品又は製品の物理的占有を保持する」という点がまさに預りを意味することとなります。
では、会計処理はどうなっているのでしょうか。
新収益認識基準における預り売上(請求済未出荷契約)の会計処理
新収益認識基準では、収益は契約で定めた義務を履行した時点で収益認識を行うとされていますが、預り売上(請求済未出荷契約)の場合の処理を以下の要件を満たした場合に売上計上できるとされています。
- 請求済未出荷契約を締結した合理的な理由があること(例えば、顧客からの要望による当該契約の締結)
- 当該商品又は製品が、顧客に属するものとして区分して識別されていること
- 当該商品又は製品について、顧客に対して物理的に移転する準備が整っていること
- 当該商品又は製品を使用する能力あるいは他の顧客に振り向ける能力を企業が有していないこと
それぞれどういう意味なのか見てみましょう。
預り売上4要件:①合理的な理由があること
預り売上の要件1つ目は「①合理的な理由があること」となっています。
先方からの要望であることを意味します。
これは分かりやすく自社が希望するだけでは預り売上の要件を満たすことはできません。
預り売上4要件:②顧客に属するものとして区分して識別されていること
預り売上の要件2つ目は「②顧客に属するものとして区分して識別されていること」となっています。
これは、預り売上の対象となっている在庫が他の在庫と区分して、客先専用のものとして識別されていることを意味しています。
既に販売されている在庫であることから、販売管理システムや在庫管理システム上も販売は不可能となっていたりする状態を示すと考えられます。
預り売上4要件:③物理的に移転する準備が整っていること
預り売上の要件3つ目は「③物理的に移転する準備が整っていること」となっています。
②とも関連しますが、②が概念上の話であるのに対して、③は実際の自社倉庫で保管している在庫が客先要望に応じて直ちに出荷等の物理的移転が可能かどうかを求めています。
預り売上4要件:④製品を使用する能力あるいは他の顧客に振り向ける能力を企業が有していないこと
預り売上の要件4つ目は「(④製品を使用する能力あるいは他の顧客に振り向ける能力を企業が有していないこと」となっています。
これは製品や商品を使用する権利を客先が有していることを求めています。
これを自由にできてしまうと客先に販売したとは言えないことから、これもある種当然の条件の一つと言えます。
以上が、預り売上計上の4要件です。最後に該当する基準も以下に記載しておきます。参考までにご覧ください。
77. 請求済未出荷契約とは、企業が商品又は製品について顧客に対価を請求したが、将来において顧客に移転するまで企業が当該商品又は製品の物理的占有を保持する契約である。
78. 商品又は製品を移転する履行義務をいつ充足したかを判定するにあたっては、顧客が当該商品又は製品の支配をいつ獲得したかを考慮する。
79. 請求済未出荷契約においては、会計基準第 39 項及び第 40 項の定めを適用したうえで、次の(1)から(4)の要件のすべてを満たす場合には、顧客が商品又は製品の支配を獲得する。
(1) 請求済未出荷契約を締結した合理的な理由があること(例えば、顧客からの要望による当該契約の締結)
(2) 当該商品又は製品が、顧客に属するものとして区分して識別されていること
(3) 当該商品又は製品について、顧客に対して物理的に移転する準備が整っていること
(4) 当該商品又は製品を使用する能力あるいは他の顧客に振り向ける能力を企業が有していないこと
まとめ


以上をまとめると以下の通りとなります。
✔ 預り売上は新収益認識基準において請求済未出荷契約として整理されている
✔ 請求済未出荷契約については以下4要件を満たした場合に収益を認識することができる
(1) 合理的な理由があること
(2) 顧客に属するものとして区分して識別されていること
(3) 物理的に移転する準備が整っていること
(4) 製品を使用する能力あるいは他の顧客に振り向ける能力を企業が有していないこと
以上、「新収益認識基準における預り売上の会計処理」という記事でした。関連する記事は以下を参照ください。