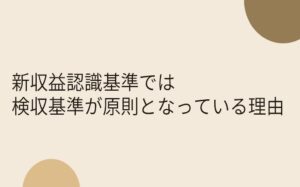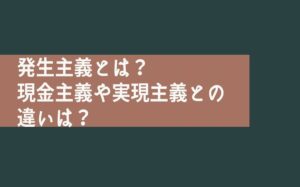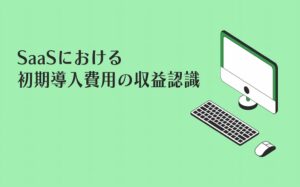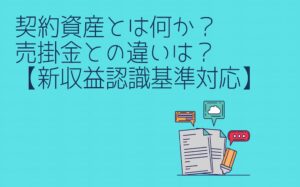悩んでいる経理
悩んでいる経理給料日は25日の会社が多いけど何か意味があるのかな?
・給料日に25日が多い理由
・給料の会計処理
給料日に25日払いが多い理由とその会計処理


今日は8月25日ということで私が勤務している監査法人でも給料日でした。マネジャーになってからは残業代が付かないため給与明細を見る楽しみは減ったのですが、昔は給料日が楽しみでした。
そんな給料日25日ですが、少し考えてみるとどうして25日なのでしょうか。気になってみたので調べてみました。
法律上で給料日を25日払いにすると決められているのか?
25日が多い給料日ですが、そもそも法律上で給料日をいつにするか決められているのでしょうか?
答えはNoです。給料日を特定の日にしないといけないと法律で決まっているわけではありません。
では、給料の支払いについて規定した法律があるのでしょうか。
これについては、労働基準法では賃金支払いの5原則というものが定められており、以下の5つとなっています。
① 通貨払いの原則
② 直接払いの原則
③ 全額払いの原則
④ 毎月1回以上払いの原則
⑤ 一定期日払いの原則
このうち給与の支払い日に関する事項は⑤一定期日払いの原則です。
これは、賃金は毎月一定の期日を定めて、定期的に支払わなければならないという原則です。
そのため、この原則さえ守れば支払日は25日である必要はない訳です。10日でも13日でも31日でもいいこととなります。
給料日に25日払いが多い理由は?
では、なぜ25日払いの会社が多いのか、調べてみると諸説あるようです。
① 月末支給だと年末年始が入ると早く支給しなければならないから
② パソコンも無い時代月初は締め作業等に忙しく25日頃が適当だったから
③ 古くは月末つけ払いが多くその少し前に給料日を設定するため
①月末支給だと年末年始が入ると早く支給しなければならないから説
この説では、月末支給だと年末年始が入ると早く支給しなければならないから都合が悪く、それであれば25日に固定した方がいいというのが理由となっています。
12月31日は銀行も会社も休みですので、12月だけ会社や銀行が休みに入る前の25日頃に支給する必要があるということでしょうか。
また、給料受ける側としては毎月の給料日が異なるよりは同日にして欲しいとは思います。
ただ、こちらの説だと25日である理由とはなっていないでしょうか。
②パソコンも無い時代月初は締め作業等に忙しく25日頃が適当だったから
2つ目の説は、昔はパソコンも無ければ経理システムも無かったので、月初から10日間前後は給与計算などをしている余裕がなかったというものです。
月初10日間は売上高の締め作業などを行い、それ以外の10日から20日の間に従業員の給与計算をして25日前後に支払いすることが多いとする説です。
確かにこの説は説得力があるかもしれません。
また、同様に以下の理由もあるようです。
月末締めで10日払いでは、残業手当てを含めるなら給与計算する期間が短く対応が難しいというものです。そのあたりのこともあって、月末に近い日になっているというものでした。
③古くは月末つけ払いが多くその少し前に給料日を設定するため
最後の説は、古くはつけで取引を行い晦日(大晦日ではなく毎月の末のこと)払いとしていることが多かったため、その払いにあわせて末日より少し前になったのが理由とするものです。
こちらは25日であることにも理由付けがあるようです。
④まとめ
いずれの説も理由は合理的な感じがしますが、25日であるとする積極的な理由はよくわかりませんでした。
個人的には③とかいい理由だと思うのですが、明確に25日とした理由かどうかは分かりませんでした。
会計上の取り扱い


最後に会計処理です。
当月末締めの25日払いで、残業代は前月分を当月支払いとします。
この場合、8月25日に支払われる給与には、8月1日から31日までの基本給と7月1日から31日までの残業代が含まれることにります。
仮に、8月31日を決算日とした場合、上記8月25日の給与は当然に処理しますが、これに加えて8月分の残業代も計上する必要があります。これは8月の残業については既に従業員から役務提供を受けており給与支払い義務が発生しているためです。したがって、8月1日から31日までの残業代を未払費用計上する必要があります。
以上、給与に関する記事でした。