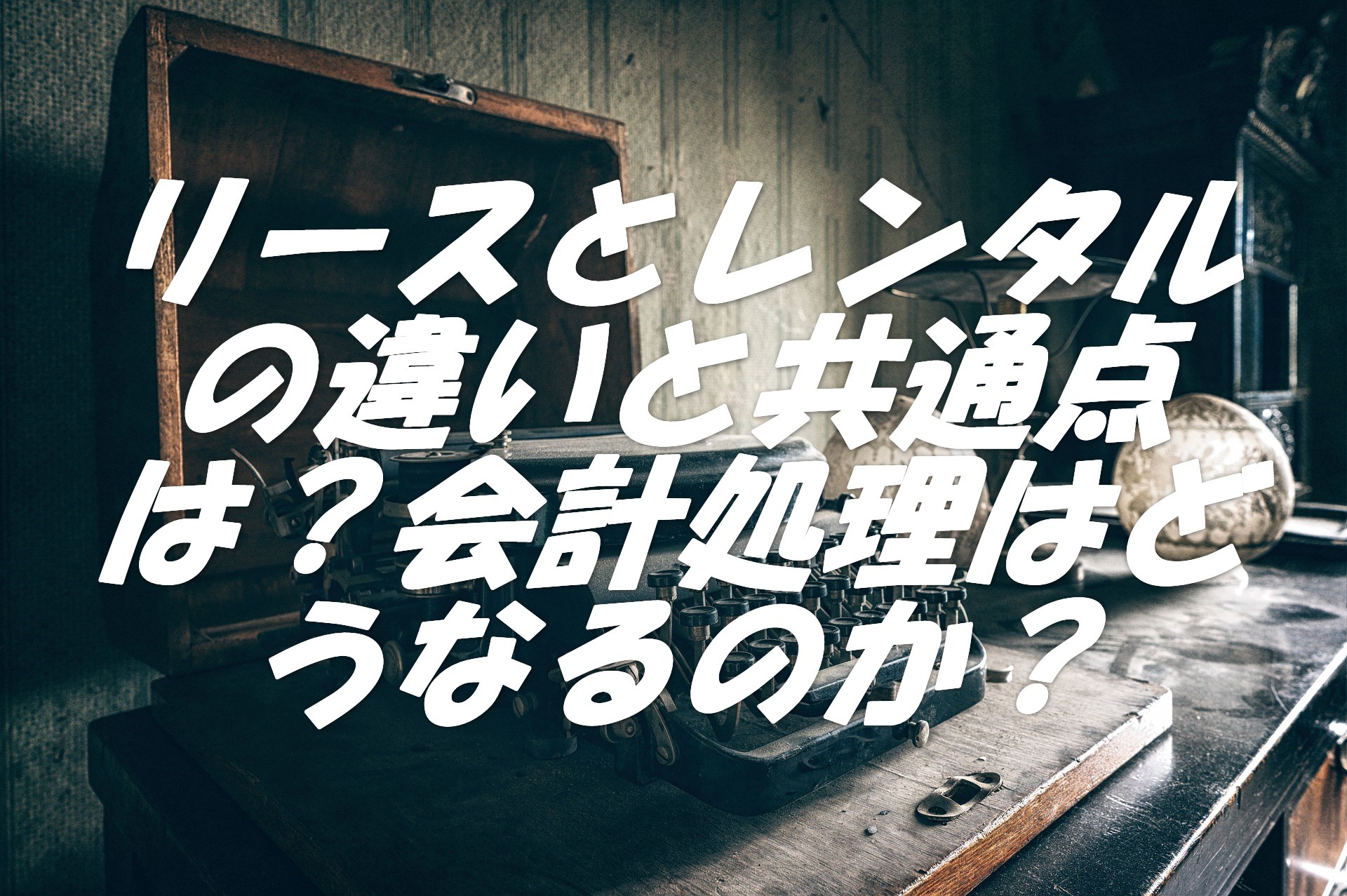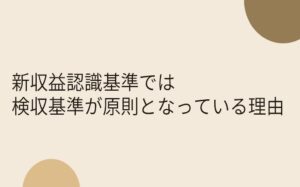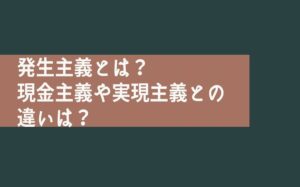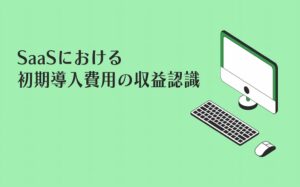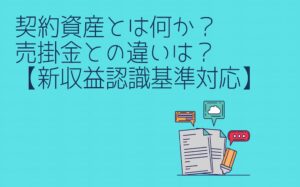悩んでいる経理
悩んでいる経理リースとレンタルってどう違うの?
会計上はどう処理するの?
会計士でも両者の違いがすっと出てこない人は多く、案外分かりにくいものです。そこで、リースとレンタルの違いや会計処理をまとめています。
記事の前半でリースとレンタルの概念の違いを説明して、後半では会計処理を説明しています。
・リースとレンタルの違い
・リースとレンタルそれぞれのメリット・デメリット
・リースとレンタルの会計処理
リースとレンタルの違いと共通点
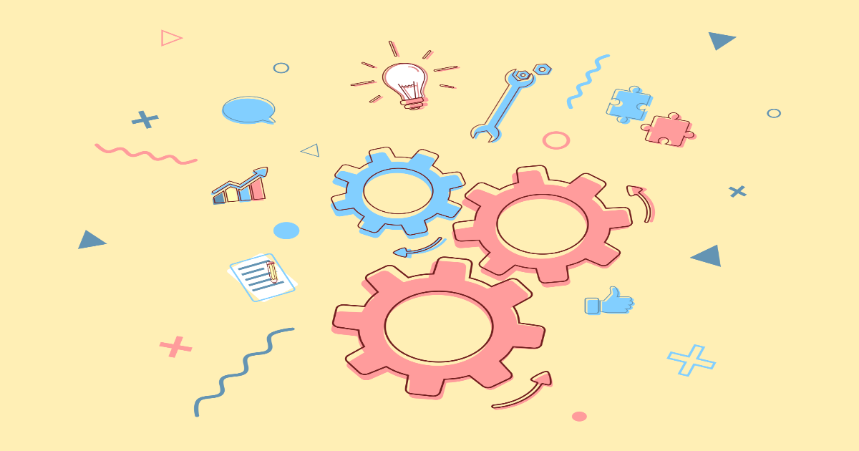
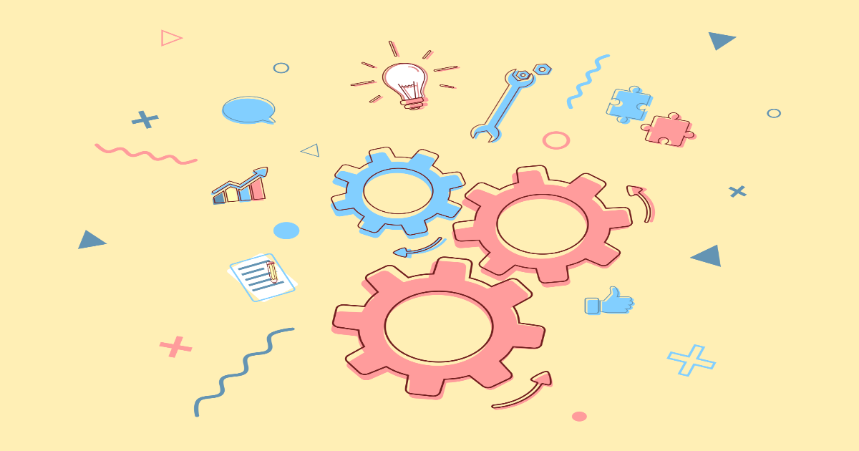
リースとレンタルの共通点はいずれも対象となるものを賃借するということですが、以下のとおり様々な点で異なっています。
| リース | レンタル | |
| 契約期間 | 中長期 | 短期 |
| 対象物件 | ユーザー側で指定が可能 | レンタル会社保有の資産から選択 |
| 中途解約 | 条件によるが不可のケースが多い | 可能 |
| 修繕 | ユーザー | レンタル会社 |
| 所有権 | リース会社 | レンタル会社 |
| 料金体系 | レンタルより高割安 | 一定 |
| 契約終了後の扱い | 返却または再リース | 返却または延長 |
| 代表的な契約例 | PCや複合機等のオフィス機器 | 建設機械など |
リースの場合はユーザーである会社がリース対象を選択して契約となる一方、レンタルの場合はレンタル会社の所有の資産から選択して契約する形が多いのではないでしょうか。
そのため、リースの場合は特定のユーザーが使い切る前提の契約となっていますが、レンタルの場合は色々なユーザーが利用することが前提となっています。
リースとレンタルのメリット・デメリット


リースとレンタルのメリット・デメリットは以下のとおりとなります。
| リース | レンタル | |
| メリット | ・最新の設備を使える ・購入するよりも初期投資は少額で使用できる | ・必要な期間だけ短期で借りれる ・事務処理負担が軽減される |
| デメリット | ・所有権がない ・中途解約ができない ・保守はユーザーで行う | ・選択肢が少ない ・短期では料金が割高 |
リースでは、対象物件をユーザーが指定可能となっていることから、最新の設備を使えるメリットがあります。また、購入するより初期投資が少ないのもメリットでしょう。
一方で、そのデメリットは所有権がない、使い切ることを前提としているため中途解約ができない、必ずしもそうではありませんが保守はユーザー自ら行うケースが多い等の点が挙げられます。
一方レンタルでは、短期からの契約が可能、保守や保険対応等はレンタル会社が実施してくれるため事務処理が軽減されるメリットがあります。デメリットしてはレンタル会社が所有している資産からのみレンタルとなるため選択肢が少ない点でしょうか。
リースとレンタルの会計処理はどうなるのか?


リース基準上はリースとレンタルの区分はない
会計上はリース契約とレンタル契約という観点で表現を分けていません。
これは、リースに関する会計基準では、リース取引を以下のとおり規定しているためです。
リース取引とは、特定の物件の所有者たる貸手(レッサー)が、当該物件の借手(レッシー)に対し、合意された期間(リース期間)にわたりこれを使用収益する権利を与え、借手は、合意された使用料(リース料)を貸手に支払う取引をいいます。
上記定義に当てはめると、一般的なリース契約もレンタル契約もいずれも同じリース取引となります。
会計上はファイナンスリース取引かオペレーティングリース取引の区分のみ
では、リース基準はどの観点から会計処理を区分しているかというと、ファイナンスリース取引かオペレーティング取引の観点からのみ処理を分けています。
ファイナンスリース取引とオペレーティングリース取引の定義は以下のとおりです。
ファイナンスリース取引とは、ノンキャンセラブルとフルペイアウトの両方の要件を満たすリース契約
オペレーティングリース取引とは、ファイナンスリース取引以外のリース契約
ノンキャンセラブルとフルペイアウトの定義は以下のとおりです。
ノンキャンセラブルとはリース期間中の中途解約が不可なリース契約
フルペイアウトは、以下2点のいずれかを満たすリース契約
①見積現金購入価額×90%≦リース料総額の割引現在価値
②経済的耐用年数×75%≦リース期間
上記に従ってリース契約やレンタル契約がファイナンスリース取引かオペレーティングリース取引に該当するか判断します。
分かりにくいのでまとめると、
ノンキャンセラブルかフルペイアウトのいずれかの要件を満たすリース契約やレンタル契約はファイナンスリース取引となり、それ以外はオペレーティングリース取引として処理する。
ファイナンスリース取引とオペレーティングリース取引の会計処理
ファイナンスリース取引とオペレーティングリース取引の会計処理をまとめると以下のとおりです。
| ファイナンスリース取引 | オペレーティングリース取引 | |
|---|---|---|
| 会計処理 | 売買処理(資産計上する処理) | 賃貸借処理(費用計上処理) |
| 償却年数 | 所有権移転の場合はリース期間 所有権が移転しない場合は経済的耐用年数 | ー |
以上のとおり、一般的なリースとレンタルという表現は会計上の処理とはマッチしない形となっています。
ただし、一般的なレンタルというものはリース基準上はオペレーティングリース契約になることが多いです。これはレンタルのケースでは多数のユーザーに利用させることを前提としているため、ファイナンスリース取引のフルペイアウトを満たさないためです。